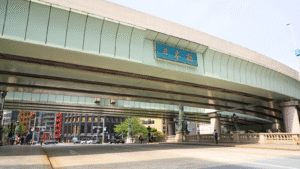IPO審査をクリアする!成長企業のためのハラスメント対策:健全な職場環境が上場への鍵
新規株式公開(IPO)を目指す成長企業にとって、事業の成長性や収益性は当然ながら重視されます。しかし、それと並んで、いやそれ以上に重要視されるのが、企業の「足腰」ともいえる健全な職場環境と強固なガバナンス体制です。特に近年、IPO審査においてハラスメント対策は、企業のコンプライアンス意識とリスク管理能力を測る重要な指標となっています。
私は証券会社の公開引受審査部で数多くのIPO案件に携わってきた社会保険労務士として、成長企業がハラスメント問題でつまずくケースを目の当たりにしてきました。なぜ成長企業でハラスメントが起こりやすいのか、そしてIPO審査で求められるハラスメント対策とは具体的にどのようなものか。本コラムでは、その核心に迫り、貴社が上場への道を盤石に進むための具体的な方策を徹底解説します。
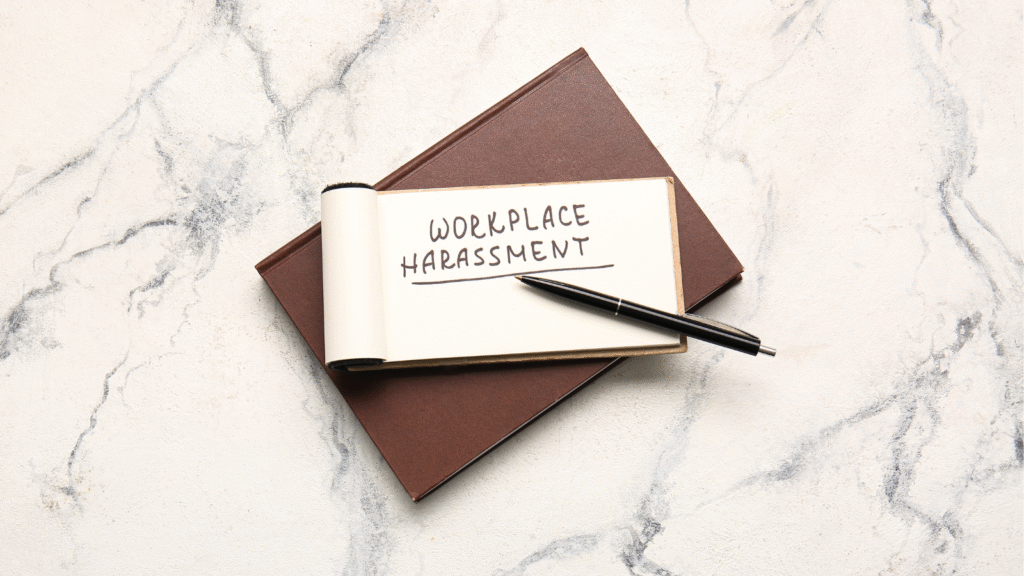
成長企業とハラスメント:なぜ問題が顕在化しやすいのか?
成長企業、特にベンチャー企業では、以下のような要因からハラスメント問題が顕在化しやすい傾向にあります。
1. 急速な組織拡大と文化の未成熟
事業の急成長に伴い、従業員数が急速に増加します。多様なバックグラウンドを持つ人材が短期間で集まるため、共通の企業文化や規範が十分に醸成されていないことがあります。これにより、コミュニケーション不足や価値観の衝突が起こりやすく、ハラスメントに発展するリスクが高まります。
2. 成果主義と過度なプレッシャー
成長企業では、高い目標達成が求められ、成果主義が浸透していることが多いです。この環境下で、リーダーがメンバーに対し過度なプレッシャーをかけたり、達成できないことに対して精神的な攻撃を行ったりするケースが見られます。また、長時間労働が常態化し、疲弊した従業員同士の衝突もハラスメントに繋がりかねません。
3. 未整備な内部統制と管理職の知識不足
急速な成長に、労務管理体制や内部統制の整備が追いつかないことがあります。ハラスメント防止規程がなかったり、あっても形骸化していたりするケースが散見されます。また、管理職自身がハラスメントに関する正しい知識を持たず、無意識のうちにハラスメント行為をしてしまったり、ハラスメント事案への適切な対応ができなかったりすることもあります。
4. 閉鎖的な人間関係と「仲間意識」の裏側
少数精鋭で始まった企業では、初期メンバー間の「仲間意識」が非常に強い傾向にあります。これは良い面もありますが、一方で外部からの意見を受け入れにくく、問題が内部で隠蔽されやすいという側面も持ちます。新しく入社したメンバーが馴染めず、孤立する中でハラスメントの対象となることもあります。 これらの背景を理解することが、効果的なハラスメント対策の第一歩となります。
IPO審査で問われるハラスメント対策の要点
証券会社や証券取引所は、IPO審査において、企業がハラスメントに対して「どのように考え、どのような対策を講じているか」を非常に重視します。それは、ハラスメントが単なる社内問題に留まらず、企業価値を毀損し、投資家へのリスクとなりうるからです。
具体的に、以下の点が厳しくチェックされます。
1. 法令遵守体制の確立
2020年6月から施行されたパワーハラスメント防止措置の義務化(中小企業は2022年4月から義務化)は、IPOを目指す企業にとって特に重要です。企業には、以下の措置を講じることが義務付けられています。
- 事業主の方針等の明確化と周知・啓発:ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発すること。
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備:相談窓口の設置、相談への適切な対応、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止など。
- 事後の迅速かつ適切な対応:ハラスメント事案が発生した場合の事実関係の迅速な確認、被害者・加害者への適切な措置、再発防止策の実施など。
IPO審査では、これらの措置が形式的に整っているだけでなく、実効性があるかどうかまで深く掘り下げて確認されます。
2. 相談窓口の実効性
ハラスメント対策の「顔」ともいえるのが相談窓口です。形式的に設置されているだけでは意味がありません。
- 誰でも利用しやすい窓口か?:社内窓口だけでなく、外部の専門家(弁護士、社会保険労務士など)に委託した窓口も設けることで、従業員の匿名性や安心感を確保できます。
- 秘密は厳守されるか?:相談者のプライバシー保護が徹底され、相談したことで不利益な扱いを受けないという信頼が醸成されているか。
- 相談後の対応は迅速かつ適切か?:相談を受けたら、放置せず、速やかに事実確認、関係者へのヒアリング、適切な解決策の検討、再発防止策の実施に至るプロセスが明確になっているか。
審査では、過去の相談実績やその対応内容、相談後の従業員の満足度などもヒアリングされることがあります。
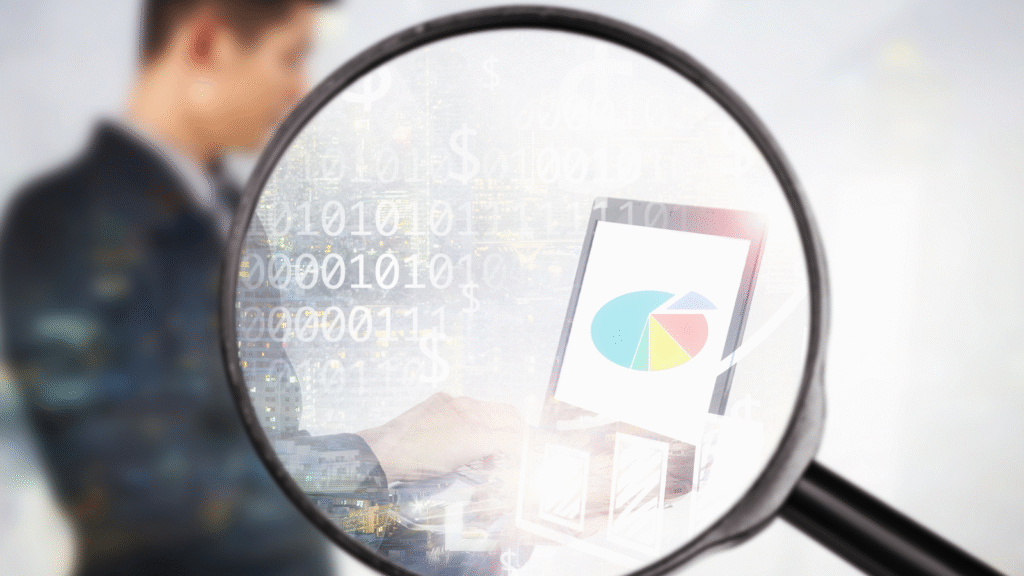
3. ハラスメント研修の実施状況
「ハラスメントは許さない」という企業の方針を浸透させ、従業員一人ひとりの意識を高めるためには、継続的な研修が不可欠です。
- 全従業員への研修:ハラスメントとは何か、どのような行為がハラスメントに該当するのか、被害に遭った場合の相談方法などを全従業員が理解しているか。
- 管理職向け研修の強化:管理職は、ハラスメントの予防だけでなく、万が一発生した場合の初期対応や、部下からの相談への適切な対応方法について、より深い知識とスキルが求められます。管理職がハラスメントを助長するような言動をしていないか、アンケート調査などで実態を把握することも重要です。
- 研修頻度と内容の適切性:研修が単発で終わるのではなく、定期的に実施され、内容も最新のハラスメント事例や法改正に対応しているか。
研修の実施記録や参加者の反応、理解度なども審査の対象となりえます。
4. 懲戒規程と運用の明確性
ハラスメント行為が確認された場合の、懲戒処分の基準と手続きが明確に定められ、実際に適用されているかどうかも重要です。
- 懲戒事由の明確化:ハラスメント行為が懲戒事由に含まれているか。
- 懲戒手続きの公正性:事実確認、弁明の機会付与、客観的な判断など、懲戒処分に至るプロセスが公正かつ透明性をもって行われるか。
- 過去の処分事例と対応:過去にハラスメント事案が発生した場合、企業がどのように対応し、適切な処分を行ったか。そして、その事案からどのような教訓を得て、再発防止策に繋げたか。
処分が甘すぎたり、逆に恣意的な運用がなされていたりすると、コンプライアンス意識の欠如とみなされます。
5. 企業文化としての浸透度
最も重要でありながら、目に見えにくいのが「ハラスメントを許さない」という企業文化の浸透度です。
- 経営層のコミットメント:経営トップがハラスメント対策の重要性を認識し、その防止に積極的に関与しているか。メッセージの発信、予算の確保など。
- 企業理念との連動:ハラスメント防止が、企業のミッションやバリューの一部として位置付けられているか。
- 従業員の意識調査:定期的な従業員意識調査(エンゲージメントサーベイ、ハラスメントに関するアンケートなど)を通じて、職場の実態を把握し、改善に繋げているか。
これらの要素は、財務諸表には表れないものの、企業の持続的な成長を支える基盤として、IPO審査では非常に重視されます。
IPO成功のためのハラスメント対策:具体的なアクションプラン
IPOを目指す企業が今すぐ取り組むべきハラスメント対策の具体的なアクションプランを提案します。
Step 1: 現状把握とリスク評価(労務デューデリジェンス)
まず、自社のハラスメント対策がどこまで進んでいるのか、何が不足しているのかを客観的に把握します。
- 就業規則・規程の確認:ハラスメント防止規程が最新の法令に対応しているか、懲戒規程は明確か。
- 相談窓口の実態調査:窓口は機能しているか、過去の相談履歴と対応状況を確認。従業員への匿名アンケートも有効です。
- 従業員意識調査:職場でのハラスメントの実態、従業員のハラスメントに対する意識、管理職への信頼度などを調査します。
- 管理職へのヒアリング:ハラスメントに関する知識や対応経験、部下とのコミュニケーションの実態などを把握します。
この段階で、潜在的なリスクや改善すべき点が明確になります。必要であれば、社会保険労務士などの外部専門家に依頼し、客観的な視点での労務デューデリジェンスを実施することをお勧めします。
Step 2: 規程・ルールの整備と周知徹底
現状把握で明らかになった課題に基づき、規程やルールを整備します。
- ハラスメント防止規程の作成・改定:パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントに加え、SOGIハラ(性的指向・性自認に関するハラスメント)やカスハラ(カスタマーハラスメント)など、多様なハラスメントに対応できる規程を整備します。相談窓口の明確化、秘密保持、不利益取扱いの禁止を明記します。
- 懲戒規程の明確化:ハラスメント行為が懲戒事由に含まれることを明確にし、懲戒の種類と程度を具体的に定めます。
- 従業員への周知徹底:作成・改定した規程は、社内ポータルサイトへの掲載、説明会の開催、書面での配布など、あらゆる手段を用いて全従業員に周知します。

Step 3: 実効性のある相談体制の構築
単に窓口を設けるだけでなく、従業員が「安心して相談できる」と思える体制を構築します。
- 社内・社外の複数窓口の設置:社内相談窓口担当者の育成(守秘義務や傾聴スキルの研修など)、必要に応じて外部専門家(弁護士、社会保険労務士)への委託を検討します。
- プライバシー保護の徹底:相談内容や相談者のプライバシー保護に関する方針を明確にし、徹底することを約束します。
- 匿名での相談ルートの確保:メールフォームや投書箱など、匿名でも相談できる仕組みを設けることで、相談へのハードルを下げます。
Step 4: 定期的な研修と啓発活動
ハラスメント対策は「一度やれば終わり」ではありません。継続的な研修と啓発活動が重要です。
- 全従業員対象の研修:年に1回程度、ハラスメントの定義、具体例、防止策、相談窓口の利用方法などを網羅した研修を実施します。オンライン研修や動画コンテンツの活用も効果的です。
- 管理職対象の強化研修:ハラスメントの早期発見、適切な初期対応、部下とのコミュニケーション方法、アンガーマネジメントなど、実践的な内容を盛り込んだ研修を定期的に実施します。
- トップメッセージの発信:経営トップが定期的に「ハラスメントは許さない」という強いメッセージを発信し、企業全体の意識を高めます。
Step 5: 再発防止とPDCAサイクル
万が一ハラスメントが発生した場合の対応だけでなく、再発防止策を講じ、継続的に改善していく仕組みが求められます。
- 迅速かつ公正な事実確認:相談があった場合は、速やかに事実関係を調査し、被害者・加害者双方からヒアリングを行います。
- 適切な措置の実施:ハラスメントの事実が確認された場合は、就業規則に基づき懲戒処分を行うとともに、被害者のケア、配置転換など、適切な措置を講じます。
- 原因分析と再発防止策の策定:なぜハラスメントが発生したのか、その根本原因を分析し、組織的な対策(例:組織風土の改善、人事評価制度の見直し、管理職への指導強化など)を策定します。
- PDCAサイクルの実施:対策の効果を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行うPDCAサイクルを回すことで、より強固なハラスメント防止体制を構築します。
健全な職場環境はIPO成功の最大の推進力
ハラスメント対策は、単なる法令遵守の義務ではありません。それは、従業員が安心して、そして最大のパフォーマンスを発揮できる健全な職場環境を創り出すための投資です。

健全な職場環境は、従業員のエンゲージメントを高め、生産性を向上させ、優秀な人材の獲得・定着に繋がります。これは、企業の持続的な成長に不可欠な要素であり、結果として企業価値の向上、ひいてはIPO成功の強力な推進力となります。
証券会社の審査担当者は、書類上の整備だけでなく、企業の「人」に対する真摯な姿勢を見極めようとします。ハラスメント対策に真剣に取り組む姿勢は、企業のコンプライアンス意識の高さ、リスク管理能力、そして何よりも従業員を大切にする企業文化を如実に物語るものです。
IPOは、企業にとって新たな成長ステージへの扉を開く一大イベントです。その扉を確実に、そして堂々と開くために、今一度、貴社のハラスメント対策を見直し、万全の体制を構築することをお勧めします。
私は公開引受審査部の経験を持つ社会保険労務士として、貴社がIPO審査をクリアし、持続的に成長できるような健全な職場環境を構築するためのサポートをいたします。具体的なご相談やご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

- 代表社員
- 開業社会保険労務士としては、日本で初めて証券会社において公開引受審査の監修を行う。その後も、上場準備企業に対しコンサルティングを数多く行い、株式上場(IPO)を支えた。また上場企業の役員としての経験を生かし、個々の企業のビジネスモデルに合わせた現場目線のコンサルティングを実施。財務と労務などの多方面から、組織マネジメントコンサルティングを行うことができる社会保険労務士として各方面から高い信頼と評価を得る。