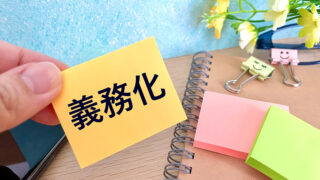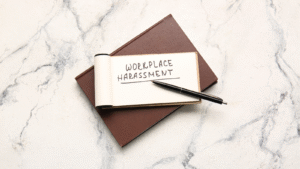地方企業がTOKYO PRO Market(TPM)を目指す上での労務上の障害と克服策:ロールモデル不在の地で描く上場への道筋
地方企業がTOKYO PRO Market(TPM)への上場を目指す際、その道のりは決して平坦ではありません。特に労務の観点からは、専門人材の不足や身近なロールモデルの不在といった、都市部ではあまり顕在化しない特有の「ハンディキャップ」が存在します。しかし、これらの障害を正確に理解し、適切な対策を講じることで、TPM上場は十分に実現可能です。
ここでは、IPOに精通し、公開引受審査の経験も持つ社会保険労務士の視点から、地方企業がTPM上場を目指す上で直面しがちな労務上の障害と、その克服策について、詳細なコラムとして解説します。
1. 「身近なロールモデル不在」という最大の心理的・実務的障害
地方企業にとって、上場企業が少ない環境は、経営層や管理職にとっての心理的なハードルとなり得ます。「上場とはどういうものか」「何から手を付けて良いか分からない」といった漠然とした不安に加え、実際に上場を経験した他社の事例やノウハウを間近で学ぶ機会が少ないことが、具体的な行動を阻害する大きな要因となります。
労務上の影響:
- 上場基準の理解不足: 本則市場と同等の労務管理水準が求められるTPMの特性や、具体的な審査ポイントに対する認識が不足しがちです。
- 準備の遅れ: どこから手を付けて良いか分からず、労務デューデリジェンスや規程整備などの準備が後回しになる傾向があります。
- 社内体制構築の困難さ: 上場企業に求められる内部統制の一環としての労務管理体制(例:担当者の配置、監査役等によるチェック機能)のイメージが湧かず、構築が進まないことがあります。
克服策:
- 積極的な情報収集と学習:
- セミナー・研修への参加: 東京証券取引所やJ-Adviserが主催するTPM上場に関するセミナー、労務管理に関する専門セミナーに積極的に参加し、最新情報や基礎知識を習得します。オンライン形式のセミナーも活用し、移動の負担を軽減することも有効です。
- 書籍・専門情報の活用: 上場準備に関する書籍や専門誌、信頼できるWebサイトからの情報収集を継続的に行い、知識を深めます。
- 外部専門家との早期連携:
- 経験豊富なJ-Adviserの選定: TPM上場はJ-Adviserによるサポートが必須です。地方企業の特性や課題を理解し、上場支援実績が豊富なJ-Adviserを選定することが重要です。J-Adviserは労務管理の観点からもアドバイスを提供してくれます。
- IPO支援実績のある社会保険労務士の活用: 地方に少ないからこそ、オンライン会議などを積極的に活用し、都市部に拠点を置くIPO支援経験豊富な社会保険労務士に依頼することを検討すべきです。労務デューデリジェンスから規程整備、労務管理体制構築まで一貫したサポートを受けることで、手探りの状態から脱却できます。
同業他社・先行事例からの学び: 地域は異なっても、TPM上場を果たした同業他社や、規模が近い企業の事例をIR情報や公開されている資料から研究し、自社に適用できる部分を洗い出すことも有効です。

2.「専門人材の不足」という構造的な課題
地方においては、労務管理、特に上場準備に必要な専門知識を持つ人材が絶対的に不足しています。社内に専門家を育成する時間も余裕もなく、中途採用も困難なケースが多いのが現実です。
労務上の影響:
- 労務コンプライアンスの不徹底: 労働時間管理、未払い残業代、社会保険の適正加入など、基本的な労務コンプライアンスにおいて潜在的なリスクが見過ごされがちです。
- 規定整備の遅れ・不備: 就業規則や各種人事関連規程が最新の法令に対応していなかったり、上場企業に求められる水準に達していなかったりすることが多々あります。
- 内部統制構築の困難: 労務に関する内部監査やモニタリング体制の構築が進まず、ガバナンス強化が滞る可能性があります。
J-Adviserや監査法人とのコミュニケーション不足: 専門用語や概念の理解不足から、円滑なコミュニケーションが阻害され、審査プロセスが長期化する可能性があります。
克服策:
- 外部専門家による「実質的な社内人材の補完」:
- 労務管理顧問契約の強化: 通常の労務相談だけでなく、上場準備を意識した労務DD、規程改定、リスク洗い出しなどを具体的にサポートしてくれる社会保険労務士と顧問契約を締結します。「貴社の経営者視点の労務の伴走者」として機能してもらうイメージを持つことが重要です。
- タスクフォースの組成: 経営層、管理部門、現場のキーパーソンからなる「上場準備タスクフォース」を社内に設置し、外部専門家がその中心となって情報共有や進捗管理を行う体制を構築します。
- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進:
- 労務管理システムの導入: 勤怠管理システム、給与計算システム、人事情報管理システムなどを導入し、労務データの正確性向上と管理業務の効率化を図ります。これにより、属人的な運用から脱却し、誰が担当しても一定水準の労務管理が行える基盤を整備します。監査法人やJ-Adviserからのデータ提出要請にもスムーズに対応できるようになります。
- オンラインツールの活用: Web会議システムやプロジェクト管理ツールを積極的に導入し、外部専門家との距離を物理的に縮め、密な連携を可能にします。
- 社内人材の育成:
限定的なOJT: 外部専門家の指導のもと、社内の若手社員や意欲のある社員を労務担当者としてOJTで育成します。全ての専門知識を習得させるのではなく、外部専門家との橋渡し役や、基本的なデータ収集・管理ができる人材を育てることを目指します。

3. 「既存の労務慣行からの脱却」という文化的な壁
地方企業では、長年の慣習や「なあなあ」な関係性の中で労務管理が行われているケースが散見されます。アットホームな雰囲気が企業の魅力である一方で、上場企業に求められる「公正性」「透明性」「画一性」とは相容れない慣行が存在することも少なくありません。
労務上の影響:
- 未払い残業代のリスク顕在化: サービス残業や曖昧な労働時間管理が常態化している場合、上場審査過程での労務DDで発覚し、多額の偶発債務として計上される可能性があります。
- グレーゾーンな手当や報酬体系: 法的な根拠や客観的な基準に乏しい手当や報酬体系が運用されている場合、見直しを迫られ、従業員との軋轢を生む可能性があります。
- 口頭での合意・ルール: 就業規則に明文化されていない口頭での合意や暗黙のルールが多く、トラブル発生時に証拠不足となることがあります。
- 従業員の反発: 長年親しんできた慣行の変更に対して、従業員からの理解を得られず、不平不満や離職に繋がる可能性があります。
克服策:
- 経営層による強いリーダーシップとコミットメント:
- 上場への目的と意義の明確化: 経営層が従業員に対し、なぜ上場を目指すのか、上場によって会社と従業員にどのようなメリットがあるのかを明確に伝え、労務慣行の変更が必要であることの理解を求めます。
- 経営層自身が率先してルール遵守: 経営層が自ら労働時間管理を徹底するなど、率先して模範を示すことで、従業員の理解と協力を促します。
- 「見える化」と「納得感の醸成」:
- 現行労務状況の可視化: 労務DDの結果を従業員にも一部開示するなど、現状の労務リスクや課題を「見える化」し、なぜ変える必要があるのかを客観的なデータに基づいて説明します。
- 新ルール導入プロセスの透明化: 就業規則や規程の改定プロセスをオープンにし、従業員代表との協議や意見聴取の場を設けるなど、一方的な押し付けではないことを示します。
- 丁寧な説明とQ&Aセッション: 新しい労務管理体制や規程について、従業員向けの説明会を複数回開催し、質疑応答の時間を十分に設けることで、疑問や不安を解消し、納得感を醸成します。
- 段階的な導入とインセンティブ設計:
- 急激な変更を避ける: 全ての労務慣行を一度にゼロベースで見直すのではなく、リスクの高い項目から優先的に、段階的に改善を進めます。
- 従業員のメリットを提示: 新しい労務管理体制が従業員の労働環境改善や、キャリア形成、モチベーション向上に繋がることを具体的に提示し、協力を促すインセンティブを設けることも有効です。例えば、残業削減によるワークライフバランスの向上や、明確な評価制度による昇給機会の確保などです。
まとめ:TPM上場は地方企業の新たな地平を拓く
地方企業がTPM上場を目指す上での労務上の障害は、確かに多岐にわたります。しかし、これらの障害は「乗り越えられない壁」ではありません。
- 外部専門家の積極的な活用
- テクノロジー(DX)の導入による効率化と標準化
- 経営層による強いリーダーシップと従業員への丁寧なコミュニケーション
これらを組み合わせることで、地方企業特有のハンディキャップを克服し、本則市場と同等の労務管理体制を構築することは十分に可能です。
TPMへの上場は、資金調達力の強化だけでなく、企業の信用力向上、優秀な人材の確保、そして何よりも地域経済の活性化に貢献する大きな意味を持ちます。身近なロールモデルが少ないからこそ、自社がそのロールモデルとなり、地域の企業を牽引していくという強い意志と覚悟が、TPM上場成功への原動力となるでしょう。
私は、IPOに特化した社会保険労務士として、貴社が抱える労務上の課題を共に乗り越え、TPM上場という目標達成に向けて全力でサポートさせていただきます。どうぞご安心ください。
投稿者プロフィール

- 代表社員
- 開業社会保険労務士としては、日本で初めて証券会社において公開引受審査の監修を行う。その後も、上場準備企業に対しコンサルティングを数多く行い、株式上場(IPO)を支えた。また上場企業の役員としての経験を生かし、個々の企業のビジネスモデルに合わせた現場目線のコンサルティングを実施。財務と労務などの多方面から、組織マネジメントコンサルティングを行うことができる社会保険労務士として各方面から高い信頼と評価を得る。