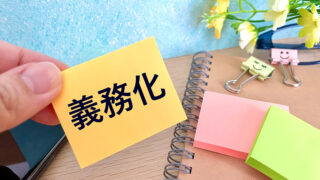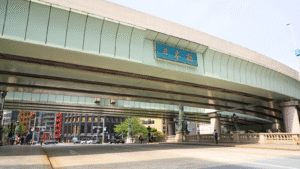IPO準備企業が直視すべき「育児介護休業法改正」のインパクト:上場を成功させる労務ガバナンスの確立
はじめに:絶え間ない労働法制の進化とIPOの要件
新規株式公開(IPO)は、企業の成長ステージを大きく飛躍させる一大イベントです。しかし、華やかな上場の舞台裏では、数多くの厳しい審査が待ち構えています。特に「労務」は、企業の持続可能性とガバナンス体制を測る上で極めて重要な要素であり、IPO審査における主要なチェックポイントの一つです。
近年、日本社会は少子高齢化、労働力人口の減少という構造的な課題に直面しており、政府はこれに対応すべく、労働法規の改正を頻繁に行っています。その中でも、企業の人材戦略に大きな影響を与えるのが「育児介護休業法」です。
2025年には、育児介護休業法が4月と10月の二段階で施行される重要な改正を迎えます。これらの改正は、企業の労務管理、人材戦略、そしてひいては企業価値に大きな影響を与えることが予想されます。
IPOを目指す企業にとって、これらの法改正への対応は単なるコンプライアンス遵守に留まりません。企業の競争力、ひいては企業価値そのものを左右する戦略的な課題として捉える必要があります。本コラムでは、2025年に施行される育児介護休業法の主要な改正ポイントを明確に分け、それがIPO準備企業にどのような影響を与え、そしてどのように対応すべきかについて、厚生労働省の最新リーフレットに基づき、具体的なポイントを交えながら解説します。
2025年4月1日施行の改正ポイントとIPO審査への影響
2025年4月1日から施行される育児介護休業法の改正は、育児関連と介護関連の多岐にわたる項目が挙げられます。
1. 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
- 改正内容:
現行では従業員数1,000人超の企業に義務付けられている男性の育児休業取得状況の公表が、従業員数300人超の企業にまで拡大されます。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかを選択して行います。年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。 - IPO審査への影響:
IPOを目指す企業の多くが、この従業員数300人超の基準に該当する可能性があります。公表義務への適切な対応が上場審査で確認されます。また、育児休業取得状況の公表は、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)側面、特に「社会」への貢献度を示す重要な指標となり、男性育休取得率が低い場合、企業の評判に悪影響を及ぼす可能性があります
2. 子の看護休暇の見直し
- 改正内容:
対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から**「小学校3年生修了まで」に拡大されます。取得事由に「病気・けが」や「予防接種・健康診断」に加え、新たに「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式」が追加されます。勤続6か月未満の労働者を労使協定により除外できる仕組みは廃止され、「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に名称が変更**されます。 - IPO審査への影響:
勤続年数の短い従業員にも休暇が適用されるようになることで、企業が従業員全体の働きやすさに配慮しているかが評価されます。就業規則や子の看護等休暇に関する規程を改訂し、実態に合わせた運用を徹底する必要があります。
3. 所定外労働(残業)の制限の対象拡大
- 改正内容:
所定外労働(残業)の制限の請求可能となる労働者の範囲が、「3歳未満の子を養育する労働者」から**「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されます**。 - IPO審査への影響:
より幅広い年齢層の子を持つ従業員が残業免除の恩恵を受けられるようになることで、ワークライフバランスを重視する企業の姿勢が示されます。
4. 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 改正内容:
3歳未満の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度について、代替措置に**「テレワーク」が追加**されます。 - IPO審査への影響:
育児中の従業員がキャリアを継続しやすい柔軟な働き方を提供できる選択肢が増えます。
5. 育児のためのテレワーク導入の努力義務化
- 改正内容:
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。 - IPO審査への影響:
IPOを目指す企業には、積極的にテレワーク導入を検討し、柔軟な働き方を推進する姿勢が求められます。

6. 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
- 改正内容:
介護休暇についても、勤続6か月未満の労働者を労使協定により除外できる仕組みが廃止されます。 - IPO審査への影響:
育児関連の休暇と同様に、介護休暇においても勤続年数による制限がなくなることで、企業の従業員に対する公平な姿勢が示されます。
7. 介護離職防止のための雇用環境整備
- 改正内容:
事業主は、介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、「研修の実施」「相談体制の整備」「事例の収集・提供」「方針の周知」のいずれかの措置を講じる義務があります。 - IPO審査への影響:
介護離職を防止するための雇用環境整備は、従業員の定着、ひいては企業の持続可能性に直結します。IPO審査では、制度の整備状況と運用実態が厳しくチェックされます。
8. 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 改正内容: 介護に直面した労働者に対し、事業主は介護休業制度等の周知と利用意向の確認を個別に行わなければなりません。また、介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、介護休業や両立支援制度等に関する情報提供を行う必要があります。
- IPO審査への影響: 従業員一人ひとりのライフイベントに寄り添う企業の姿勢として評価されます。
9. 介護のためのテレワーク導入の努力義務化
- 改正内容:
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。 - IPO審査への影響:
介護においてもテレワークの活用が努力義務化されることで、従業員が介護と仕事を両立しやすくなります。これは、高齢化社会における企業の社会的責任を果たす姿勢として評価されます。
2025年10月1日施行の改正ポイントとIPO審査への影響
2025年10月1日に施行される改正は、育児期の柔軟な働き方の実現に焦点を当てています。
10. 柔軟な働き方を実現するための措置等(育児期)
- 改正内容:
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、「始業時刻等の変更」「テレワーク等」「保育施設の設置運営等」「養育両立支援休暇の付与」「短時間勤務制度」の5つの措置の中から2つ以上を選択して講ずる必要があります。 - IPO審査への影響:
多様な働き方の選択肢を提供することが義務化されるため、従業員個々のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を支援する企業の姿勢が示されます。これは、従業員満足度向上に直結します。
11. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
- 改正内容:
(1) 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取: 事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取しなければなりません。
(2) 聴取した労働者の意向についての配慮: 聴取した労働者の意向について、自社の状況に応じて配慮することが義務付けられます。 - IPO審査への影響:
従業員のライフステージに応じたきめ細やかなサポート体制が構築されているかという点で評価されます。
IPO準備企業が今から取り組むべき労務戦略
2025年4月・10月改正を念頭に、IPOを目指す企業が今すぐ取り組むべき労務戦略は以下の通りです。

1. 就業規則・育児介護休業規程の総点検と改訂
2025年4月1日および10月1日の施行日に間に合うよう、最新の法改正内容が漏れなく反映されているかを確認し、必要に応じて改訂します。公表義務の対象拡大に対応したデータ収集と公表方法、介護離職防止の措置、育児期柔軟な働き方実現措置の義務化など、多岐にわたる項目を精査する必要があります。
2. 労務管理体制の強化と担当者の教育
人事・労務担当者が、最新の法改正内容を正確に理解し、従業員からの問い合わせや申請に適切に対応できるよう、定期的な研修を実施します。管理職向けにも研修を導入し、育児・介護休業が取得しやすい職場環境づくりを組織全体で推進します。
3. 育児休業取得状況の可視化と改善計画
従業員数300人超の企業は、公表義務を念頭に、現状の育児休業(特に男性育休)の取得状況をデータで把握し、取得率向上に向けた具体的な改善計画を策定します。正確なデータ収集と分析ができるよう、人事システムの整備も検討します。
4. ハラスメント対策の再徹底
育児・介護休業取得を理由とした不利益な取り扱いやハラスメントは、IPO審査において極めて厳しくチェックされます。就業規則におけるハラスメント防止規定の再確認、相談窓口の周知、相談への迅速かつ適切な対応、再発防止策の徹底が不可欠です。
5. 専門家による労務デューデリジェンスの活用
IPO準備の最終段階では、外部の専門家(社会保険労務士、弁護士など)による労務デューデリジェンス(労務DD)の実施を強く推奨します。厚生労働省の「中小企業育児・介護休業等推進支援事業」では、社会保険労務士等の専門家が無料でアドバイスしてくれます。DDを通じて指摘された事項は、IPO申請までに確実に改善し、是正報告ができるように準備を進めることで、上場審査をスムーズに進めることができます。
おわりに:労務戦略は企業成長の礎
2025年の育児介護休業法改正は、企業にとって「育児・介護と仕事の両立支援」をより一層強化することを求めるものです。IPOを目指す企業にとって、これらの改正への対応は、上場審査を通過するための必須条件であると同時に、持続可能な成長を実現するための重要な投資と捉えるべきです。
「人」を大切にし、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる環境を整備することは、企業の生産性向上、イノベーション創出、そして優秀な人材の獲得競争における優位性確立に直結します。これは、投資家から見ても、企業の長期的な成長性と安定性を評価する上で極めて重要な要素となります。
IPOは、企業にとって新たなステージへの挑戦です。この挑戦を成功させるためには、財務諸表の美しさだけでなく、企業の「人」に対する真摯な姿勢と、それを支える強固な労務管理体制が不可欠です。2025年の育児介護休業法改正への適切な対応は、その最たる例と言えるでしょう。
本コラムが、IPOを目指す企業の皆様にとって、労務戦略を見直し、上場を成功させるための一助となれば幸いです。
投稿者プロフィール

- 代表社員
- 開業社会保険労務士としては、日本で初めて証券会社において公開引受審査の監修を行う。その後も、上場準備企業に対しコンサルティングを数多く行い、株式上場(IPO)を支えた。また上場企業の役員としての経験を生かし、個々の企業のビジネスモデルに合わせた現場目線のコンサルティングを実施。財務と労務などの多方面から、組織マネジメントコンサルティングを行うことができる社会保険労務士として各方面から高い信頼と評価を得る。